「天気予報によれば、天気の良いのは今日一日だけらしい。我々は今日のうちに山へ登らねばならない。」 私はそんな意味の言葉を英語で運転中のディートリッヒに伝えた。
「ねばならない!?」 「ウィー ハフ トウー!?」
彼はチューリッヒの空港のハーツレンタカーで借りたBMW525iのハンドルを握りながら思わず私の顔を見た。
六月も終りの金曜日、スイス.チューリッヒ郊外のウインタートゥールで仕事を終えた我々は、その晩、ホテルのテラスのレストランで、彼はマスのムニエルを、私は子牛のストロガノフを夫々ハウスワインの白と赤を飲みながら胃を満たし、初夏の心地よい風をほろ酔い加減の頬に感じながら週末のスケジュールを話し合った。
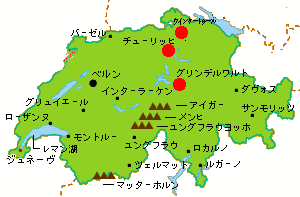
ネスレのHP上の地図を改良
なるべく早く出発したい私と少しでも遅くまで寝ていたいディートリッヒとの間で遠慮がちな悶着があったものの翌朝七時半にはホテルウィンタートゥールを発った。
スイスの地図など買わずに、大きな欧州道路地図の一部をコピーしたものしか持っていない彼は、案の定チューリッヒを過ぎて二時間程走って道に迷い、山に囲まれ静かに水を湛えた湖に出てしまった。私は只彼のハンドルに頼るしかなく、湖水に張り出した白壁のレストランの窓辺に咲き誇る紅紫色のペチュニアや湖上に走るヨットを眺めながらディートリッヒが道を聞くのを待っていた。
「分かった。今度はパーフェクトだ。前の人が間違って私に教えたんだ。」
確かにそれからはハイウェーを順調に飛ばし、横に長い二つの『湖の間』と言う意味のインターラーケンに近づくにつれて氷河に削られた荒々しい風貌の山々が迫り、真昼の光芒に雪と氷が鋭角に見上げた私の眼の中でハレーションを起こし始めた。あまりの眩しさに視線を落とし車窓に飛び行く柔らかな牧草や若葉に眼を休めたものの、また直ぐにその眩い頂きに眼を奪われてしまう。車は既にグリンデルワルトの谷に入り始めている。
十六年振りのグリンデルワルト。標高千五百メートルの天国。緑の絨毯の上に点在する家々と、そこから急角度で天を突くアイガー、ユングフラウの急峻で重厚な岩と氷の大伽藍にもう直ぐ会える。晴れ間よ続いてくれ。そして私はディートリッヒに言った。
「我々は今日のうちに山に登らねばならない。」
彼は運転しながら半ば唖然として私の顔を見て言った。
「ねばならない!?」 「ウィー ハフ トウー!?」
私も一瞬彼の顔を見つめ返しながら彼の短い質問の意味を理解した。
そう、私にとって山に囲まれたグリンデルワルトの村はこの旅の出発点なのに、ディートリッヒにとってはそこが終着点だった。仕事以外では、行動の同質性を求めたり強制されることこそ彼らの最も嫌う事なのだろう。
山の好きな私は、十七年前初めて夢に見たアイガー、ユングフラウに登った。
一方、旧東独のバルト海沿いの寒村で生まれたディートリッヒはライプチヒの有名な光学機器メーカでエンジニアとして働いていたが、当時の独裁政権に睨まれ抹殺のブラックリストに彼の名前が載ったという情報を知り、私が平和なグリンデルワルトを訪れた同じ十七年前の晩秋のある夜、妻と六歳になる長男と三歳の次男を連れて着の身着のまま文字通り決死の覚悟で壁を超えて西ドイツに亡命した。
ベルリンの壁が崩壊するまでにはその後まだ六年を要した。西独政府は彼を手厚く保護し、大学の街として有名なハイデルベルク郊外のアパートに住まわせた後、アーヘン工科大学の研究員として職を斡旋し、その後の研究で博士号を取得した。
そんな彼にとって、美しい桃源郷の様なグリンデルワルトの村は、そこに滞在しのんびりとデッキでアルプスの陽光を浴びながら好きなビールを飲むことが充分に旅の目的なのである。
ホテルに着いたら直ぐに着替えてケーブルの乗り場に飛び出して行こう等と考える最大公約数的日本人の行動パターンを採ろうとした自分に気が着いて心の中で頬を赤らめた。
チューリッヒの取引先に予約してもらったホテルアルピナは、グリンデルワルト駅から北に急な坂道を歩いて五分程登った所に有る。真紅のゼラニュームのフラワーポットを横一列に窓辺に並べたホテルは、そう呼ぶより山荘と言うほうが適切な風情である。家族と香港のホテル学校から勉強に来たというアルバイト学生達とで運営している様で、肩肘張らないアットホームさが心地よい。
早速我々は綺麗に健康的に伸びた芝生の庭のテーブルで、ボイルした自家製ソーセージのマッシュポテト添えとピルツビールの昼食を取った。真昼の光に輝く緑の絨毯の谷を隔ててアイガー北壁が真正面に聳え立ち、カラフルなパラセーリングが優雅に舞う。
「ディートリッヒ、素晴らしい景色だなー!」私はもうボルテージが上がりっぱなしである。
「イエス」と答えながら彼はアイガーの方角に一瞥を呉れソーセージを食べている。実に素っ気無い。
昼食後結局我々は友好的にお互いの意志を尊重して別れ、ディートリッヒはその辺をブラブラしていると言う。私は部屋に戻ってデイパックに防寒具を兼ねた雨具とミネラルウォータ、スイスチョコを詰めて、フィルスト行きのロープウェーの乗り場へ急いだ。
4人乗りのキャビンはグングン高度を稼ぎ標高二千百メートルのフィルストまで一気に上がる。
左手にはベッターホルン(注1)の頂きがもうほぼ水平な目線の先にあり、谷を隔てて正面には氷河と岩肌が日本では決して見ることの出来ない高さにまで突き上げている。
暫し眺めて、高山植物の咲き乱れる雲上の小道を歩いてアルプ(注2)へと下って行った。
夕闇が迫り雨雲がその暗さを増しポツポツと来た頃、村のメインストリートまで降りてきたらディートリッヒに出会った。お互いに満足そうな顔をしている。
「ディートリッヒ、チョコレートアイスクリーム食べたろう?」
「何故分かる?」
「口の脇に付いているよ」
二人とも腹の底から笑った。
(注1) 『ヴェッターホルン』は アイガー(今井通子さんが北壁を登って有名)の山塊に対峙している。
(注2)『アルプ alp』は辞書には『特にスイスの高山』と書いてありますが、日本の近代登山の黎明期(大正〜昭和初期)のアルピニスト(優れた文人も多い)がスイスの山に遊び、その著書に『アルプ』と度々出場するのは、『高山の麓』といった意味で使われています。標高で云うと15百米〜20百米位の場所でしょうか?